(1) O.クレンペラー/シドニーso. ハールストーン・コラール・ソサエティ V.バナル(S) F.テーラー(A)
50.9.23 or 25L Town Hall, Sydney Mono
(2) O.クレンペラー/VSO. アカデミーcho. I.シュタイングルーバー(S) H.レッスル=マイダン(A)
51 Vienna (Vox) Mono
(3) O.クレンペラー/ACO. cho. J.ヴィンセント(S) K.フェリアー(Ms)
51.7.12L Concertgebouw, Amsterdam (Holland Festival) Mono
(4) O.クレンペラー/PO. cho. E.シュヴァルツコップ(S) H.レッスル=マイダン(A)
61.11.22-24/62.3.15,24 Kingsway Hall, London (EMI) Stereo
(5) O.クレンペラー/VPO. cho. G.ヴィシネフスカヤ(S) H.レッスル=マイダン(A)
63.6.13L Vienna Mono
(6) O.クレンペラー/バイエルンRso. cho. H.ハーパー(S) J.ベイカー(A)
65.1.29L Herkules Saal, Munich Stereo
(7) O.クレンペラー/NPO. cho. A.フィンレイ(S) A.ホジソン(A)
71.5.16L Royal Festival Hall, London Mono
DHR-7759

この演奏のテンポは非常に速い。このCDには、この演奏を含めたこの曲の演奏時間が掲載されていますが、これによるとクレンペラーの演奏の中でもこの演奏が一番短いものです。71年のNPO.とのものに比べると全体で30分以上短く、EMIのスタジオ録音と比べても12分以上短いようです。以前に何かの本で、この曲の最短と最長の両方の記録はクレンペラーだ、という文章を読んだことがありますが、この録音が出たことにより自己記録を更新したことになります。
| I | II | III | IV | V | Total | EMI録音との差 | |
| シドニーso.(50.9L) | 16:43 | 9:14 | 10:14 | 3:48 | 27:04 | 67:04 | -12:09 |
| VSO.(51) | 19:00 | 10:00 | 11:41 | 4:13 | 30:41 | 75:35 | -3:38 |
| ACO.(51.7.12L) | 17:36 | 9:18 | 10:24 | 4:01 | 29:32 | 70:51 | -8:22 |
| PO.(61&62) | 18:59 | 10:29 | 11:37 | 4:02 | 34:06 | 79:13 | 0 |
| VPO.(63.6.13L) | 19:26 | 10:13 | 11:24 | 4:02 | 33:08 | 78:12 | -1:01 |
| *PO.(63.12.19L)(CD-R) | 19:54 | 10:24 | 11:32 | 4:22 | 33:19 | 79:31 | 0:18 |
| バイエルンRso.(65.1.29L) | 20:13 | 10:37 | 11:54 | 4:05 | 32:07 | 78:56 | -0:17 |
| NPO.(71.5.16L) | 25:36 | 12:51 | 13:49 | 5:11 | 41:23 | 98:50 | 19:37 |
上記の表のように、クレンペラーの演奏は全部で7種がCD化されています(CD−R盤を含めれば8種)。これはBeethovenの5番やSchubertの8番などと並んで最も録音の多い部類に入ります。Mahlerでは勿論一番多い数です。スタジオ録音は別として、実際演奏会でMahlerを振る際、クレンペラーといえばこの曲、というお得意演目といった印象は本人にも招聘先にもあったのでしょう。
このCDのリーフレットにある当日のプログラムによると、この演奏は、50年9月23日と25日の2回、同プログラムで行われており、前半にBachの管弦楽組曲3番を置いていました。このCDに収められている演奏がどちらの演奏なのかは、CDにも記されていません。
この演奏でまず気づくのは、第1楽章と終楽章のテンポがかなり速い、ということです。クレンペラーのMahlerはスタジオ録音で聞いても決して遅いテンポではないので、ライヴということを考慮してもこれはかなり速いものです。特に第1楽章でそれが顕著です。EMI時代以降のほとんど演奏効果を無視したようなインテンポの演奏とは違って、あちこちでアッチェランドをかけるので、余計テンポが加速されます。こういった演奏は50年代初めまでのクレンペラーの特徴で、恐らく解釈とか演奏効果といったことより、どちらかというとこの指揮者が過去からずっと持っていた演奏様式から来ていることだと思います。特にこの曲の第1楽章と終楽章は劇的効果をもった楽章で、クレンペラーの指揮振りもかなり意志的な表現をみせています。歌唱は英語です。
なお、このCDはオーストラリアでの貴重な録音ではあるものの、音はかなり貧弱です。
アルト・ソロはEMI盤のスタジオ録音にも参加しているレッスル=マイダンで、年が若かったこともあるのか他の演奏より端正な歌い振りです。
終楽章は後年の録音にも劣らない音楽の作りです。勿論、演奏様式の点では遙かに力感あふれた指揮ぶりではありますが、この雑多な素材を詰め込んだ楽章の全体像を掴んだ上での的確な演奏だと思います。空間的な広がりや上昇感覚といった感覚は薄いですけれども。
音質ですが、1楽章はかなり音揺れがあります。時代からくる録音上の制約から仕方のないことかも知れません。もう少しいい音で聴きたいところですが、同年のACO.との録音が残されているので(それも驚くような高音質で)、この時期のクレンペラーを知る上ではそちらのほうがいいでしょう。
ところで、ある著名な音楽評論家がクレンペラーのEMI時代以前の演奏を評して、二流と断じていますが、これを二流から一流に変貌を遂げたというような単純な言い方で済ましてしまうならば、大事な問題が抜け落ちてしまうような気がします。作曲も演奏も時代の様式があります。当然、その時代の要請から来るものもありますし、個人的な要因によるものもあります。録音された一個の演奏について云々するのであれば、そうした言い方が出来ますが、ひとりの指揮者として考えれば、そう簡単に断じることは出来ないでしょう。EMI以前のクレンペラーの演奏には明らかに戦前のクロール・オペラ時代の表現主義的演奏様式の残照がありますし、EMI時代になってからも特にライヴにおける演奏には多分にその名残りが見えます。
1楽章の冒頭、クレンペラーの出だしというのは、EMIのスタジオ録音を含めて割と素っ気なく始まります。音楽は6番あたりと並んで劇的な音楽だと思いますが、それを殊更強調しないでどちらかというと静かな調子でスタートします(Vox盤とは少し違う印象)。
クレンペラーはこの年の5月、Mahler没後40周年記念演奏会についてのウィーンにおける放送ンンタビューで、第2交響曲を追悼記念の曲目とした理由を尋ねられ、次のように答えています。
なぜならこの交響曲は一種の葬儀のようなものだからです。次のようなクロプシュトックの言葉に作曲された合唱とともに締め括られます。「塵である汝は復活するだろう。しばしの眠りの後に」。これ以上申し上げる必要はないでしょう。この曲はマーラーの交響曲の中で最も葬儀に相応しいものです。(「クレンペラー 指揮者の本懐」)
Mahler自身、この第1楽章を「葬式を示す」と書いています。
今風の音響的効果に注目すれば、冒頭のこの主題(動機)は印象的に鳴らすのが普通のやり方で、バランス的にもその方が効果が上がります。ヴァイオリンとヴィオラがフォルテ2つで入り、2小節目から低弦がフォルテ3つで特徴的な主題を奏でますが、ここでクレンペラーは意外とも思えるくらい強調していません。クレンペラーが強調しているのは第1楽章に記されたAllegro maestoso(厳粛に)の方だといってもいいかも知れません。
第1楽章も全体的にクレンペラーとしてはパッショネイトな演奏ですが、特徴的なのはやはりフェリアーの歌の後、最終楽章の表現でしょう。強弱とテンポの収縮が大きく、ACO.の明快な音色とテクニック(金管にいくつかのミスはあるものの)に支えられて壮麗な「復活の歌」が奏でられます。私はこの曲に感じられるある種の宗教的なストーリー性を前提とすることには抵抗があるのですが、それでもこのACO.との響きは、同じフランドルの大画家ルーベンスの光を感じさせます。
音も含めて、この演奏はEMI時代前のクレンペラーが為し得た表現主義的演奏の一つの頂点とも言えると思います。
独唱陣のうち、アルトは、フェリアーです。言うまでもなく、ワルターVPO.の「大地の歌」でパツァークとともに歴史的名盤を残しています。このワルターとの演奏は52年5月のものですから、この演奏はその前年、死の前々年のものということになります。P.ヘイワースの著書によるとこの頃のフェリアーは病後でかなり体調が悪かったということです。声にそれが出ているか否かについては、私にはわかりませんが、ワルターの盤と同様、深い声質の朗々とした歌い振りです。わたしはフェリアーの演奏をそう聴いているわけではないので何とも言えませんが、彼女の声は他のアルト歌手に比べてもかなり特徴的な声に聞こえます。クレンペラーの演奏に何度も付き合っているルートヴィヒともまるで違いますし、この曲のスタジオ録音盤でのレッスル=マイダンとも違います。メゾではなく本当にアルト音域の恰幅のある深い声質で、オペラでは異質に感じられるような声だと思いますが、Mahlerでは実に雰囲気が出ています。例えばルートヴィヒはその訓練された均一な声質をコントロールして、歌を表現しているのですが、フェリアーの場合は声そのものに劇的な要素を持っていて、歌うことだけで表現が完了してしまうような感じがしないでもありません。これは才能とか、技巧とかの問題ではなくて、声質そのものの違いです。声域は違いますが、ちょっとJ.ノーマンを思い出させる声質です。
このコンサートで、フェリアーはMahlerの「亡き児をしのぶ歌」も歌っていて同じくDecca盤で聴くことが出来ますが、この共演での両者はかなり険悪なムードだったようです。コンサートの後、フェリアーは友人への手紙の中でクレンペラーを「感情もなく事務的でとんでもない奴」と書いていますので、クレンペラーの態度はかなり冷淡なものであったようです。これはフェリアーひとりに対してのことではないかもしれませんが、クレンペラーの性格から考えると、芸術的な資質の問題は別としても皮肉の一つや二つは言ったかもしれません。しかし、クレンペラーは、前年の12月10日、同じACO.との「大地の歌」でフェリアーと共演したときのことを、後に「それはすばらしい出来でした」と回想しています(「クレンペラーとの対話」)。これから考えると、人当たりの極端に悪い(と言うより、人気のある人間には辛辣な態度をとる)クレンペラーもフェリアーの芸術性については十分認識していたということでしょう。(本当に性格は悪いですね。クレンペラーはSchönbergのことをじつにいやな奴だ、と言っていますが、人のことが言える性格ではない)
尚、「大地の歌」を共演した時のプログラムは、他にオランダの作曲家H.Henkemansの独奏によるMozartのピアノ協奏曲K.503でした。(この曲はクレンペラーが唯一スタジオ録音をしたMozartの協奏曲です。)
第1楽章は「劇的」というより「静的」な雰囲気の漂う演奏です。スタジオ録音ということで精緻に音を拾っていく、といった印象。他の指揮者による音響的に華やかな演奏に比べると、あくまでも「厳粛」な演奏と言えます。クレンペラーにとって、この楽章の基本的な解釈が明確に表れています。
スケルツォはむしろ穏やかな雰囲気を持っています。この演奏では、第2楽章とこの楽章を2つの性格の違う中間楽章と捉えて、本来のスケルツォ的諧謔味を意識して抑えているような演奏。
4楽章から終楽章にかけては全体的に、テンポを抑えたことからくる重量感とスケールを感じさせます。またスタジオ録音の強みでしょうか、舞台裏の金管が鳴る合唱直前の部分では、寂寥感さえ漂い、ちょっと浮世離れした感覚に襲われます。
レッスル=マイダンはVox盤に比べより深みを持った歌唱、シュヴァルツコップは流石にしっかりとした安定感のある声です。特にシュヴァルツコップの訓練されたコントロールと均一な声質や過多にならない表現は、(ルートヴィヒにも感じることなのですが)、オペラもリートも一級品だったこの人のすごさを改めて感じさせてくれます。
クレンペラーの演奏の重心が4楽章から最終楽章の部分にあるのは明らかです。クレンペラーのこの曲に対する姿勢というのは、Decca盤のところでの引用でもわかるように、現代の日本人である我々からみるとちょっと大時代的な印象があります。宗教的に無頓着な者にとってちょっと想像できない世界です。Mahlerにとってもクレンペラーにとっても宗教的な土壌は同じであって、これは「理解する」といった対象ではありません。しかし、Mahlerが生きていた世紀末ウィーンの閉塞感から疑似宗教的な救済の道を表現しようとしたことは確かで、これは想像以上にMahlerの「個」、クレンペラーの「個」に関わっていると思います。この曲の各楽章につけられた説明を必要以上に受け入れる必要はないと思いますが。
私がLP時代にこの演奏を初めて聴いたときの印象は、4番や「大地の歌」でのストイックなまでの造型感覚、建造物を思わせる強固な安定性に比べると、終楽章が重い不格好な演奏ではないか、というものでした。これは、LP時代にレコードを裏返したり取り替えたりすることから、CDの時代になって、スタートボタンをポンと押すだけ(それも聴く体勢が出来てからリモコンで)になったという、機器操作上の違いによる印象の差もあったのでしょう、CDで聴き直してその思いは若干改善されましたが、それでもこの演奏はプロポーションが美しいとは言えないと思います。
作曲者自身が第1楽章の後少なくとも5分の休憩をとるように語ったこと、第2楽章と第3楽章のテンポはその性格の違いがあっても一連の流れになっていること(ここの部分は、Berliozの幻想交響曲を世紀末的感傷とアイロニーに置き換えたような感じですね。シチュエーションは違いますが)、短い4楽章は終楽章へアタッカで繋がっていること、こうした構成は、実は指揮者でもあったMahlerの演奏効果を得るためのかなり綿密な計算があったのではないか、と思います。私は本に書かれていることを割と漠然と考えていましたが、Mahlerが演奏する側でもあったこと、つまり作曲者が演奏効果を確かめながら曲を校正できるというこの上もないポジションにいたわけですから(事実リハーサル中に楽譜を書き直していたくらいですから)、これは当然と言えば当然のことです。
Mahlerの1番は古典的な楽章構成を持っていますが、この曲はかなり変則的な構成です。ひとつはそのアンバランスな楽章の長さ、もう一つは終楽章の異例とも思える長さと複雑な構成です。いかにもMahler的だと言えばそれまでなのですが、それは現在第10番まで通して聴ける我々の感覚なのであって、この曲を作曲していた時点でのMahlerにとってもこの構成は確かに変わっている、という感覚はあったと思います。4楽章の「原光」と呼ばれる楽章は終楽章の暗示的序奏と見なせば、曲全体は、声楽なしの1から3楽章、声楽入りの4,5楽章に大きく分けられます。勿論、内容的にも、作曲者自身が様々なところで書き残している説明でも同様です。ただ、問題だったのは、このバランスでしょう。Mahlerはこの曲を作曲した時点ではまだ後の作品のように不均衡であること(単に時間的なものだけではなく)が積極的に作品自体にもたらす美点を信用しきれていなかったのかもしれません。例えば、SchonbergのようなMahlerにとっては新しい作曲家のようには吹っ切れていないところがあります。恐らく、生涯完全には吹っ切れなかったでしょう。音楽に限らず、現代の芸術ではこの不均衡は手段でも技法でもなく、既に前提でさえあります。ゲーテの言葉を借りれば「古典派」と「ロマン派」を分ける指標は健康的か否か(こんなに単純ではないんですが)、ですが、MahlerとSchonbergを分けるのは、様式の不健康を意識できたか、あるいはその意識すべて取り込んで自らを様式化できたか、ということではないかと思います。
Mahlerは、均衡のとれた古典的楽章構成についてはこだわっていなかったのですが、多分演奏上の効果として、声楽なしの部分と声楽入りの部分のバランスに苦慮していたのではないでしょうか。巨大な終楽章と均衡させるため、前半の1楽章は印象的でなくてはなりません。5分の休憩の指定はそのためでもあるのです。2楽章と3楽章は、形式的には古典的な手法で対比効果を持たせがらもストーリー的連続性を維持して散漫になるのを防ぐ配慮が見られます。これでなんとか終楽章とのバランスを保てます。
歌入りの4楽章から終楽章にかけてですが、これはちょっと複雑です。(私は楽譜を見ながら聴いてもはっきりと作りが見えてこないので困ります。)
終楽章の声楽が入る前の部分、(解説書等ではこの楽章は3部に分けられると書いてあるうちの1、2部部分)は、音楽としてはたいそう立派ではあるものの雑多な要素がつながっていて集中力を維持することが難しいような気がします。一応、提示部と展開部といった形式をとっていますが、印象としては、Mahlerがクロプシュトックの歌詞を見いだす前に書き進めていた色々な楽想を捨てきれないままにここに詰め込んでしまったような感じがします。その結果、音楽自体の起伏はあるものの、構成を維持する緊張感は、歓喜の予感という情緒的な要素に多くを負うことになってしまい、有機的に演奏することがかなり難しい曲になったように思います。
クレンペラーのこのスタジオ録音では、終楽章の部分(特に上述の1,2部)が今一歩突っ込みに欠けているのか、少し張りがないようで、前半3楽章までとの対比が鮮明でないうらみがあります。私がこの演奏に感じているバランスの悪さはこのあたりから来るものかな、と思います。確かに素晴らしい演奏ではあるのですが、この録音後のライヴ、特にバイエルンRso.との鮮明な演奏と比較するとそうした感が強くなります。
第1楽章冒頭から気迫のこもった低弦の響き、まず音の強さに圧倒される思いです。かなりデッドな音質でVPO.の美音を聴くというわけにはいきませんが、逆にその音質も手伝ってか集中力の強い強靱な音楽が聴けます。整ったEMIのスタジオ録音とも違いますし、突っ走る50年代の表現主義的演奏や晩年の強固な構築物を感じさせる演奏とも違います。感覚としては、50年代の最良の部分を60年代の器に収めた、とでも言えましょうか。
特に弦の強さと合奏力の素晴らしさは特筆されるべきでしょう。VPO.とは知らなくても最優秀なオーケストラだということはわかります。
各楽器の、特に弦楽器のフレーズに独特の抑揚があることが、この演奏の力感と推進力につながっていると思います。アタックも力強いのですが、その後もう一段押し込むような独特の弾き方をします。その結果、音符の表層をなぞっていくような薄い音ではなく、フレーズのふくらみを作って実体感が出てきます。これがVPO.に特徴的な弾き方かどうかちょっとわからないのですが(色々聴いてきたにもかかわらず情けないとは思いますが)、とにかくPO.との演奏にはない弾き方です。
終楽章では、興に乗ってきたのでしょうか、VPO.の強力な管セクションもパワー全開の素晴らしい演奏です。この辺までくると聴いていて少し体が熱くなってきます。「復活の讃歌」での高揚感も圧倒的で、クレンペラーの数ある「復活」の中でも最も「興奮する」演奏です。
独唱陣は、ロストロポーヴィチ夫人でもあるロシアの名ソプラノ、ヴィシネフスカヤとVoxへのスタジオ録音以来度々歌っているレッスル=マイダンのコンビ。ヴィシネフスカヤの声はまさに鋼のような強さ、占領地の町を駆け抜ける装甲車のごとき有無を言わせぬ強靱さ、東西雪解け前のロシアのオーケストラに聞かれた金管群と例えればよいでしょうか、本当にそういう質の声です。オーケストラに限らず、ロシアの独特の響きというのがあるのだな、と妙に納得した次第。オペラティックな歌唱ですが、やはり圧倒的な存在感です。これに対してクレンペラーの2つのスタジオ録音でも聴かれるレッスル=マイダンの歌はヴィシネフスカヤと張り合おうとしたわけでもないでしょうが、EMI録音と比べると少々不安定な感じがします。
Desqes Refrein盤はこの時期のライヴ物としては音に潤いがなくデッドな音です。M&Aからも同じ演奏が出ていますが、似たような音質らしく、この演奏内容を考えると非常に残念です。迫力という点ではクレンペラーの第2の中でも随一で、68年のBeethovenやSchubertとの演奏のようにいい音の盤が出現すれば圧倒的な名演となるでしょう。
この演奏も出だしが弱い(おまけに縦の線が合っていない)。EMIスタジオ録音以上に厳粛な入りですが、恐らく一番重々しさを強調していない演奏でしょう。バイエルンRso.はドイツのオーケストラとは言え、重さを全く感じさせません。技術的に非常に高いのは聴いてすぐわかりますが、それにも増して各楽器の音が抜群に綺麗です。金管の存在感のある音、木管の表情豊かな歌いまわしの魅力はEMIのスタジオ録音を凌ぐものがあります。クーベリックのMahler全集の録音が始まるのはこの少し後くらいからですが、そうした関係もあったのでしょうか。クレンペラーの解釈はそう変わってはいないのに、この演奏は、強固な造型というより、肌触りの良い空間の広がりを感じます。
第2楽章は曲のつくりもあって、弦の巧さが際立っています。PO.の演奏がしっかりとしたマッスのコントロールで聴かせるのに対し、バイエルンRso.はボリュームの伸縮が自然でフレーズの呼吸が生きています。非常に美しい演奏です。
スケルツォはPO.盤より決然とした雰囲気のティンパニで開始されますが、全体はむしろ力感より美しさを表面に打ち出したような演奏です。
4楽章のアルト・ソロはJ.ベイカーです。明晰でいながら柔らかみも深みもある端正な歌です。個人的にはこの人の歌は大好きで、クレンペラーの演奏の中ではフェリアーよりベイカーをとります。続く5楽章は冒頭からスタジオ録音には見られないような高揚感があります。この楽章でもオーケストラの反応の良さは素晴らしいと思います。上述しましたが、私がスタジオ録音で不満だった点もここでは全く気になりません。
ソプラノはベイカーとともに「真夏の夜の夢」でも共演しているH.ハーパーですが、この人の声も深みも伸びもある良い声で、2人の声の絡む部分はスタジオ盤でのシュヴァルツコップとレッスル=マイダンとはまた別の美しさです。
音はホールトーンも良く録られていますし、何よりクリアな響きが素晴らしいと思います。この時期のライヴとしては申し分ない音質とコンサートプレゼンスを持っています。まるで販売を考慮したような録音で、バイエルン放送局の録音技術の高さに感謝したいくらいです。
第4楽章では、ホーレンシュタインの「大地の歌」でも歌っているホジソンが登場しますが、初めはなんとか合わせているものの、Ach nein ! Ich liess mich nicht abweisenと2回繰り返す部分の後半で堪えきれずに先行してしまいます。
終楽章の遅さは極めつけ。リタルダンドして止まりそうになるというのとは違いますけれども、普通の人間にしてみれば限界と思えるテンポを延々と維持し続けるのは、逆にその気力に感心してしまうほどです。合唱が入り、ソプラノとアルトのソロが登場するあたりで少しテンポが上がるような感じがしますが、これはクレンペラーがテンポを速めたと言うより声楽陣が歌いやすいテンポに引き上げた印象です。
テンポがテンポですから、2人のソロはさぞ歌いにくかったでしょうが、フィンレイの気品のある愛らしい声、ホジソンのしっかりとした声ともこの曲には相応しいと思います。
この演奏の評価は難しいと思います。どう贔屓目に見ても良い演奏とは言えません。また、解釈の仕方、という言い方も無理があります。クレンペラーの演奏は60年代最後の2,3年あたりから更に遅くなってきて(曲にも依りますが)、70年代にはほとんど限界に近いテンポとなりました。結果、スケールの大きな音楽となったものも確かにあるのですが、これは明らかに身体的、精神的老化の為せる業だと思います。
尚、このCDのリーフレットにも音盤化されている7種の演奏の演奏時間が掲載されています。Doremi盤とは秒単位で数字が異なっていますが、これは計り方の誤差程度のもので、同レーベルでも盤によって違いがあることもしばしばです。(ただしVPO.との演奏における終楽章の時間が36:36と記載されているのは、Doremiのリーフレットに比べると3分以上長くなっています。Desque Refrain盤の表記によるとこのArkadia盤表記の方が間違っていると思われます。)
この盤が市場に出た頃は、まだシドニーso.とのDoremi盤とエジンバラ音楽祭での63.12.19の録音(CD-R)は出ていませんでしたから、計算上6種となる筈ですが、実はここには62.3.4のPO.との演奏というのが載せられています。この録音はどこのレーベルで出ているのかわかりません。参考に載せます。
| I | II | III | IV | V | Total | EMI録音との差 | |
| PO.(62.3.4L) | 19:40 | 10:32 | 11:30 | 5:56 | 32:10 | 79:48 | 0:35 |
私のグスタフ・マーラーの思いでは、はるか昔に遡る。彼とは1905年にベルリンで知り合った。オスカー・フリートが、マーラーの第2交響曲を指揮したときである。この曲はその10年前の1895年に書き上げられたのだが、当時の批評家たちの意見は、マーラーは詐欺師、いかさま師、天才気取りの男であるなどというものだった。
1905年には批評はいくらかましになっていたが、まだ良くはなっていなかった。私は22才という若さであったが、第2交響曲の演奏では、光栄なことに舞台裏のアンサンブルを指揮することができた。聴いていたマーラーは私に満足していたようであった。その後、ヴィーンで職を得ようと骨折ったが、それが徒労に帰したとき、マーラーが推薦状を持たせてくれた。私はプラハのアンジェロ・ノイマンのもとで3年間を過ごし、再びマーラーの推薦でハンブルクに赴くことになる。1910年、ミュンヘンでの第8交響曲の練習でマーラーに会ったのが最後になった。1911年5月18日に彼は亡くなったのである。(「指揮者の本懐」)
この第2交響曲の演奏の後、クレンペラーは「マーラーの関心を惹くのは唯一自分の作品」というO.フリートの助言に従い、2手ピアノ編曲版を作ってMahlerを訪ねました。Mahlerは自分の曲を暗譜で弾くことに随分驚いたようです。これ以降、クレンペラーの指揮者としての歩みが本格的に始まったわけです。O.フリートの録音は、ホーレンシュタインの「亡き児をしのぶ歌」がカップリングされているPearl盤で聞くことが出来ます。
フリートは、1871年ベルリン生まれ、戦前はPolydorに、MahlerのほかBeethoven,Brahms,Bruknerなどドイツ系大曲の録音をかなり残しており、Polydorにとっても重要な指揮者であったことを窺わせますが、ナチ台頭後、ロシアに渡り大戦中の42年に亡くなりました。クレンペラーの恩人であると同時に、Mahler存命中からその作品を演奏し、紹介に努めた人でした。上述の第2交響曲演奏時、クレンペラーは22才の若造であったわけですが、フリートも30代半ばになるかならないかの頃で意気盛んであったのでしょう。クレンペラーは「20世紀の最初の20年間、彼はベルリンで新しい作品をすすんで取り上げる唯一の指揮者だった」と述べています。
Polydorへの録音は23年、この曲の最初の喇叭吹き込みです。音質は推して知るべしですが、雨音の向こうから聞こえる音楽から当時の様子は窺えます。演奏は総じてテンポの動きがあり、気分の交錯が強調されているかのようです(クレンペラーの演奏を聴いた後では、余計気になります)。遅いテンポはより遅く、速いところはより速く、といったところでしょうか。めまぐるしく変わるテンポは、良く言えばメリハリのついた、悪く言えばせかせかとして落ち着かない演奏です。
スケルツォから終楽章にかけては色々な音が全面に出てきて面白い。文字通りプカプカ、バタバタの連続。
4楽章はE.ライスナーという人が歌っています。当然この時代ですから発声の古さは仕方ないのですが、ここは意識的にテンポを遅く採っているようです。終楽章の合唱が入るまでは、やはり楽想の交代に合わせてかなりテンポの動きがあって、時代性を感じさせるのは仕方ないと思います。
この頃の録音風景というのはどういうものだったのでしょうか。グラモフォンのデータ・ブックにはオーケストラ伴奏歌曲の録音らしい写真が掲載されています。この写真は1908年頃となっていて、喇叭のまわりにいろんな楽器がごちゃごちゃ寄り集まって、まるで列の詰まったマーチングバンドのような感じです。フリートの2番が録音された頃はもう少し改善されていたとしても喇叭で音を拾うことには違いありません。
それでも、この演奏の響きがどうのこうのというのは別問題として、演奏様式についてはMahlerの意図をある程度反映していた可能性はあります。Mahlerは実際フリートの演奏を聴き、助言もしていたからです。しかし、十分人数を揃えて録音しているわけではありませんから、コンサートでの演奏を喇叭用に誇張して演奏していたこともあったと思います。
CDX2 5521

POCL-3902(国)
Verona
27062/63
 |
 |
5 67255 2
EMI
SLS 806(英LP)
 |
 |
DR910007-2

5 66867 2
Nuova Era
6714-DM
Hunt
CD 703
 |
 |
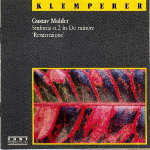 |
2CDHP590
