この編曲は外部からの依頼によってのものではなく、純粋にSchönbergの個人的な趣向の産物でした。この理由を後にA.V.フランケンシュタインへの手紙(1939.3.18)の中で説明しています。
1.非常に好きな作品であること。
2.この曲がほとんど演奏されないこと。
3.演奏されても酷い演奏ばかりで、特に良いピアニストになればなるほど音が大きく、弦が聞こえない。私は一度すべての音を聴いてみたい。
そして編曲への配慮として、Schönbergの言葉を借りれば「厳格にブラームスの様式の中にとどまり、かりにブラームスが現在生きていたとしても、彼自身が行おうとしたと思われること以上のことはしないように」行われました。確かに音楽そのものはあまり変えていない(Brahmsの音を変更しない)ようですが、特に第4楽章の楽器編成とオーケストレーションはかなり自由で、Brahms自身がやったなら絶対こうはならない、といった響きです。
Schönbergは、ウィーンからベルリン時代にも学生に作曲を教えていましたが、そこでは12音音楽には全く触れなかったようです。アメリカに渡ってからも同様で、ちょうどこの頃に書いた作曲の教科書(確か「作曲の基礎技法」という本ですが、今手元にないので間違っていたら訂正します。)の中でも基本的に古典派からロマン派までの作曲家の譜例でアナリーゼしていていますが、それは基本的に、しっかりとした音楽家になるための実践的技法というべきものです。(残念ながら、私にはその端くれにでもなれるような才能もありませんから、その点では猫に小判ということになりますけれど、これは随所にそれぞれの作曲家に対するSchönbergの技法上の指摘があって読み物としても面白いものです。)Schönbergの12音技法は、理論的な発想とドイツ音楽への愛情と純粋な熱意から出発していますから、ほとんど無味乾燥な音列になりかねないその音楽に、伝統の継承としての音楽の装いを付加しなければなりませんでした。音楽としての統一性や多様性の獲得といったことはもちろん、それより重要であったのはまさにBachやMozartやBeethovenの伝統を技法的に内包することによって後継者たり得ることでした。私にはこれが、方法論的、というより感情的にそうであったと思われます。この技法的アナリーゼは、そういう面ではSchönbergにとって最も重要な作業だったでしょう。J.Straussの編曲は食い扶持のためだったかもしれませんが、例えばBachの編曲は、「もう一度Bachを作曲する」という作業が重要だったのではないでしょうか。
Brahmsのこの編曲についてSchönbergはこう述べています。
当然に多くのむずかしい問題があった。ブラームスは、きわめて低いバスを好んでいて、そういう音に対してオーケストラは少数の楽器しかもっていない。ブラームスは、しばしば違うリズムの分散和音をもつ充実した伴奏を好んでいる。そして、これらの音型の多くはブラームスの様式の中で一般に構成的な意義をもっているので、たやすくは変えられないものになっている。私は思うに、これらの問題を自分は解決したと思う。しかし、私が成し遂げたことは、現在の音楽家たちには大きな意味を持っていないだろう。というのも、こうした問題を知らないからである。そして、そういう問題があるのだと彼らにいったところで、彼らは感心を示さない。だが私には、そういう問題がとにかく意味があるのだ。
何故、そういう問題が彼にとって特に意味があったのでしょうか。ここには、Schönbergの音楽家としての同胞の意識と偉大な先達への尊敬が隠されているように感じます。そして「Brahmsの曲を作曲する」ことへの義務感のようなものがあったのではないでしょうか。だから「ブラームスの第5」という呼び方は、Schönbergにとって最大の誉め言葉であったに違いありません。既に12音技法を確立していたSchönbergは、実は1曲ぐらい古典的な楽想と技法で好きなように作曲してみたかったのかもしれません。
この編曲を取り上げている指揮者は大きく3つに分けられるでしょう。クレンペラーの初演時の貴重な録音は別として、Schönberg側からのアプローチとして、現代音楽の専門家のツェンダー、ギーレンあたり、こうしたキワモノ好きなロジェストヴェンスキー、サイモン、ヤルヴィ、その他音楽的にBrahmsとSchönbergの両方にまたがる人たち、といったところでしょうか。
私の知る限りでのこの曲のCD化されている録音を以下に挙げました(録音順)。また、CD期になってからの録音はこれ1曲では収録時間に余裕があるのでカップリングする曲にも配慮されており人によってはなかなか面白い組合せです。
第2楽章 Intermezzo - allegro ma non troppo
第3楽章 Andante con moto
第4楽章 Rondo alla Zinarese - presto
ARC-114/115

38.5.7L Philharmonic Auditorium, Los Angeles 12:03/8:36/9:12/7:22
この曲の初演の記録で、こんな録音が残っていたのかと正直言って驚きでした。Archiphon盤に載っている当時のプログラムでは前半にBrahmsのセレナード第2番op.16(表記によればこの曲は当時ロサンゼルスでは初演であったらしい)、後半にこの曲が演奏され、クレンペラーとしてもかなり意欲的な演奏会であったようです。音質はかなり貧弱で雑音も多く、途中音の大幅な途切れ(原盤はディスクでしょう)や音程、音量の揺らぎなどあって聴きづらい音ですが、当時の雰囲気は伝わってきます。現代の総じて遅めでBrahmsのロマン性や舞曲的特性とSchönbergの多彩なオーケストレーションを両立させようとした演奏ではなく、戦前の現代音楽の旗手であったクレンペラーがその演奏スタイルで為し得た貴重な記録。いくらクレンペラーでもアメリカでこの曲をやるには色々苦労があったでしょう。
演奏は通常の古典的交響曲様式を踏襲したような構成で、2楽章は典型的な緩徐楽章として捉えられているようです。3楽章は部分毎に割と性格的に振り分けている印象で古典的な緩急のコントラストをつけた演奏。終楽章はテンポが速く、新しい他のどの演奏と比べてもより激しいパッションを持っていてオーケストラも完全には弾き切れていません。音は相当欠落しているもののインテンポで一気に進むところはクレンペラーの古い演奏スタイルそのものと言って良いでしょう。エンディングの凄まじい勢いは一聴の価値があります。
クレンペラー本人も晩年この曲をもう一度振りたいと言っていましたが、もし実現していたらどんな演奏になっていたでしょうか。
CD 311 034

78 13:24/7:47/10:50/9:14
全体にダイナミック・レンジが狭い若干こもったような録音。響きもデッドな感じ。少なくとも録音で聴く限り弦主体のバランスで、木管金管群は印象が薄い。そのためSchönbergの色彩的なパーカッシヴな華やさはあまり感じられません。
1,2楽章はそれほど特徴的ではないのですが3楽章以降はかなり粘りのある大きなうねりをもった没入した表現(録音によるのか低弦が強い)です。響きは重厚ですが、やはり録音のせいかいまひとつスケールを感じさせません。歌い廻しやテンポ設定なども特にこれといった強烈なインパクトがないのが惜しいですね。今の若杉氏であればもっと良い演奏が出来ると思いますが、この時期にこの曲をヨーロッパで取り上げていたということは驚きです。
私がこの曲のことを知ったのは、P.ヘイワースの「クレンペラーとの会話」を読んでからでしたが、初めて聴いたのは、NHK-FMで放送された若杉弘指揮のベルリンRso.との演奏でした(77.9.19L)。このケルンRso.とのCDがSchwannから出た時は、そうした思い入れもあって大いに期待したのですが、演奏は前者のほうが感動的だったように思います(これは初めて聴いたという感激もあったのかも知れません)。
カップリングはBergが2台ピアノ用に編曲したSchönbergの第1室内交響曲op.9。アンソニー&ヨゼフ・パラトーリの演奏。
0021582BC(DG原盤)

79 14:05/8:30/10:22/9:00
70年代としては驚くほど鮮明な音で、楽器の分離も申し分ありません。現代音楽としてのSchönbergの音楽を考えればこの演奏は正に模範的な演奏と言えるでしょう。過去のしがらみを持たないシャープな音は現代音楽のスペシャリストとしてのツェンダーの美点であろうと思います。しかし演奏そのものは決して軽くはなく、ひとつひとつの音がタペストリー的に次々に現れ、時に先鋭に響き、時に意外なほど重層的に響きます。音楽は見通しが良く、Schönbergが書いた音符ひとつひとつが実に明確にその居所を持っているといった感じ。これは他にちょっと聴けない独特の演奏で、鮮烈な音の響きとメカニカルな切れ味だけでもこの演奏は非常に面白く聴けます。
オーケストラは1974年の創立のドイツの若手演奏家で構成された団体。ここでのツェンダーの指揮にも全く無理なくついていっていますし、特に反応が良さは特筆されます。このオーケストラは様々な指揮者とともに既にかなりの録音がありますが、そのいくつかを聴いた限りではどれも大変若々しく明るいストレートな音で、技量も全く不足ないと思います。この演奏の非常に現代的な響きも恐らくこのオーケストラの特性が反映されているのではないでしょうか。
この録音は元DGのLP。この盤でのカップリングは同じオーケストラでベルティーニ指揮、Webernの管弦楽のためのパッサカリアop.1とMahlerの交響曲10番アダージョ。ツェンダーの乾いた音の作りとは正反対で面白いです。
S.701(独LP)

82.11.24L Beethovensaal des Konzerthauses Stuttgarter Liederhalle
南ドイツ放送の自主制作LP。上記の若杉盤やツェンダー盤が70年代にリバイバルさせたこの曲が、既にヨーロッパ各地で人気を博していたことを窺わせる録音で、冒頭に指揮者による曲解説が収録されています(恐らく演奏前に会場の聴衆に向けたスピーチ。独語)。拍手つきのライブ。
Schonbergの奇抜なオーケストレーションを前面に出すことなく、細部に気を配った極めてしなやかな演奏。第1楽章の出だしなど、本当に密やかで、びっくりします。テンポは全体に遅く、最近の演奏に比べれば微温的ともとれそうな演奏ですが、これが劇場を主な活動の舞台としているこの指揮者の特徴なのか、或いは、新しい音楽を分かりやすいように聴衆に紹介するためのサービスなのか分かりません。ただ、オーケストラで奏でるBrahmsの室内楽曲という視点では、演奏も丁寧ですし、オーケストラもしっかりしています。
ACD8196

83 13:38/8:32/10:13/8:55
細かい音まで拾う録音ではないので、カラフルなオーケストレーションの綾を楽しむという訳にはいかないのですが、レーベルのせいもあって全く話題に上らない割にはオーソドックスなまとまりを持った演奏。本当はもう少し録音に分解能があって、スパッと音抜けが良ければ聞こえ方も違うのでしょうが。
終楽章の小気味の良いリズムとテンポが秀逸。決して切れ味が良いと言うのではないのですが、変にもたれるようなところがなく、と言って味気のないリズムでもない。いくつかの演奏はこの楽章のテンポを随分いじくり回すので(響きの大仰さとは別に)曲の締まりがなくなってしまうものがありますが、このテンポは私の好みですね。一聴したところでこれといった特徴がない演奏と言えばそうなんでしょうが。
1枚物で時間には余裕があるのですが、カップリングはなし。
TOCE-9715(国)

84.6.19 The Maltings, Snape, Aldeburgh 13:59/8:19/10:50/9:16
ラトル80年代半ばの演奏。若々しいけれど節度を失わない非常に充実した演奏です。開放的なオーケストラの鳴し方と音響バランス、そして大きく自然な解釈がここでも生きています。音は決して派手ではないけれど、暖色系、弦が少し薄いのはオーケストラのせいでしょうか。
1,2楽章は力感はありませんが、細部まで気が配った丁寧な作りで、適度なコントラストをつけながら響きを上手くコントロールしています。3楽章もゆったりとしたテンポで丹念に進めていく印象。行進曲風の中間部でもテンポを上げず、殊更それを強調しているわけではないのですが、音量ではここがひとつのクライマックス。その後のいかにもBrahms的な穏やかな楽想の広がりは、鮮やかな対照となっていてラトルの巧さを感じさせるところです。終楽章の華やかなオーケストレーションは楽器の音色を生かした良い演奏です。テンポははじめ速めですが中間部は十全に歌うゆったりとしたテンポ。再び速いテンポから一気に最低音域まで崩れ落ちるような下降線をたどった後一旦終止してカデンツァ風の部分を経てコーダに向かうのですが、このあたりの自然なテンポの緩急が鮮やかです。コーダの迫力も圧倒的。
ただ、難点を言うと、クライマックスと設定している部分の音響だけが突出している感じで、私にはちょっと違和感があります。意図は分かるのですが例えばコーダあたりはもう少し締まった音で終わってほしい、という気がします(録音の仕方にも関係するのかな)。恐らく今のラトルであればもう少し力感というか、陰影のしっかりしたスケールの大きい演奏が可能だと思うんですけれど。(BPO.で再録音したら素晴らしい演奏になりそうですね)
私がこの曲を初めて買ったのがこのラトルの国内盤LPでした。LPではカップリングはなかったのですが、左は来日記念に国内発売された2枚組CD。トゥーランガリラ交響曲がメインの組合せ。
IM 42129(独LP)

85L Herculessaal, Munich 13:53/7:41/9:52/8:16
これは長らく聴いたことがありませんでしたが、偶々LPを入手することができました。ジャケットの表記によれば、これは純然たるスタジオ録音ではなくライブからの編集により制作されたもののようです。ただし、拍手等はなく、通常ライブに聞かれるような会場のノイズもありません。
重厚な演奏ではないですけれど、オーケストラの鳴り方は十分です。何よりティルソン=トーマスの指揮がすばらしい。明確なフレージング、確固とした音楽の輪郭、大きなダイナミクス、ついつい演奏に聞き入ってしまいます。Brahmsの曲というよりSchonbergのオーケストレーションを際立たせる演奏といえるでしょうか。
金管や打楽器系の効果的な使用はこの編曲の最も重要な点です。Brahmsの原曲を損ねるほどの派手なオーケストレーションはSchonberg自身の弁解じみた自己解説を必要としたのでしょうが、その醍醐味と目論見はこの演奏で見事に再現されていると思います。
録音は初期のデジタル(SonyのPCM1610システム)ですが、非常にクリアでDレンジも広く取れています。
カップリングはSchönbergのオーケストレーションによるBachのコラール「装いせよ、わが魂よ」BWV654と「来たれ、創り主、聖霊なる神よ」BWV.631。
CHAN8825

88 St Jude-on-the-Hill, Hampstead Garden Suburb, London 15:10/9:11/11:54/9:25
ヤルヴィ独特の強いアクセントと馬力、濃厚なロシア的歌い口で非常に重厚な演奏になっています。テンポは全体に遅く、トータルではロジェストヴェンスキーに次いで遅い演奏。弦や木管の響きは時折Tchaikovskyを思わせるような表情が聞こえたり(特に第3楽章!)、3楽章半ばの行進曲風の部分では軽やかさや切れというものが全くなく、恐ろしいくらい派手に重厚にオーケストラを鳴らすといった部分は、「十全に歌いきる」といったロシア系の演奏の面白さがあります。フレーズの処理も実にロシア的で、アゴーギク等も西側の指揮者とは全然違って面白い。
終楽章はSchonbergの多彩なオーケストレーションの見せ場でもありますが、ここでのヤルヴィの重量感というのも凄い、の一言。ストコフスキーを思わせるようなテンポの動きと独特の節回しに加え、オーケストラの鳴りは凄まじい。込み入ったSchönbergのオーケストレーションの妙味を味わうのではないのですが、大オーケストラのための派手な曲のこれ又思いっきり重い演奏が聴けるという点では実に面白い盤です。
丁度この頃からCDのみの発売となりカップリングする曲もトータルにデザインされるようになりました。この盤のカップリングはヘンデルの主題による変奏曲とフーガop.24をE.Rubbraが編曲した版、これは珍しい。
TOC 93-75

89.10.26-28L Severance Hall, Cleveland 12:35/8:01/9:20/8:31
クリーヴランドo.75周年記念のボックスに含まれている演奏。先日リリースされたセル来日時のSibelius交響曲2番も一足早くこれに収められていました。ドホナーニの演奏はこの他にBeethovenの大フーガ、Ruggles「太陽を踏む者」、Schubert交響曲第10番D.936A~アンダンテ(P.Gulke編)。
ライヴとは言え、非常に整った演奏で録音も実に自然な音です。クリーヴランドo.も全く気負いがなくてあたかもやり慣れている曲を演奏するかのように余裕がありますし、音も引き締まっていながら、柔らかさも感じさせ適度の量感もあります。ただドホナーニの指揮にはこれと言った特徴はないように思います。全体に響きも良く洗練された演奏なのですが、どうも何か物足りません。後年のVPO.との演奏と比較するとやはりコンセプトが定まっていないというか、まとまってはいるものの安全運転という感が拭えません。元々ドホナーニという人は堅実な指揮をする人であまり極端な解釈をすることはないと思いますが、それであればこうした機能的なオーケストラを使って表現できる何かがあると思います。
決して悪い演奏と言っているのではなく、この組合せではもう少し高い次元の演奏が可能ではなかったでしょうか。
11752

90.3 St Jude-on-the-Hill, Hampstead Garden Suburb, London 15:19/8:33/13:07/9:45
ロジェストヴェンスキーは70年代終わり頃Melodiyaにもこの曲を録音しているようなのでこれは2度目の録音ということになります。とにかくテンポが独特。第1楽章は遅いテンポで鬱屈した暗い雰囲気、第2楽章も同様で意外におとなしい。3楽章は極端と言ってよいほど遅い。マーチ風の部分はそれこそ考えられないほど遅く、綺麗に揃った隊列の行進をスローで見ているようなところにShostakovich的な際立って正確なサイド・ドラムが加わり独特な雰囲気。終楽章は少しテンポが上がりますがそれでもかなり遅い方です。途中、テンポを上げるところはいくつもあるのですがことごとく遅いままで、チャールダーシュ的な緩急交替のコントラストはありません。唯一エンディングでアッチェランドをかけて勇壮に終わります。
とにかく独特の演奏。これだけ遅いテンポは個人的にはあまり好みではないのですが、こういう演奏もあるんですね。
ロジェストヴェンスキーのこの曲がリリースされたときは、結構期待したのですが、思っていたのと少し違いました。ロジェストヴェンスキーは旧ソ連時代に自国のオーケストラを振る時は結構派手に鳴らして面白かったのですが、どうも西側のオーケストラでは解釈は別としても今ひとつ面白味に欠けるような気がします。遠慮でもないのでしょうが、少しはじけ方が足りないんでしょうか。同じテンポで良いからソヴィエト文化省o.との演奏のように暗い空間から音が飛び出してくるような演奏であればまた違った面白さがあったような気がしますが。
カップリングはロジェストヴェンスキーらしく凝っていて、Rachmaninovの練習曲集「音の絵」から作曲者自身が選んだ5曲をRespighiがオーケストレーションしたもの。クーセヴィツキーが依頼したもので、翌31年12月ボストンso.と初演されました。こういう曲に目を付けるロジェストヴェンスキーもすごいですが、こうした編曲を当時の大作曲家に次々に依頼していた(Ravel編の「展覧会の絵」が有名ですね)クーセヴィツキーもすごい人です。
CACD1006

90.10.1&3-4 St Jude-on-the-Hill, Hampstead Garden Suburb, London 13:06/8:01/10:15/8:34
こういった秘曲珍曲の類が大好きで自分のレーベルまで作ってしまったオーストラリア生まれのジェフりー・サイモンが、恐らく最もやりたかった曲のひとつがこの曲だったのではないでしょうか。
サイモンの演奏は、細かい部分まで目の行き届いた非常に明確な響きとLSO.の見事なアンサンブルによる鳴りの良さに特徴があります。テンポは中庸。殊更意識したテンポ設定ではありません。Brahmsの感傷味を帯びた弦のうねりも実に良く表現されていて特に3楽章後半などでは本当にBrahms自身の交響曲を聴いているような錯覚を覚えます。終楽章の速めのテンポは切れの良いリズム感でもたれませんし、エンディングのクライマックスへのもって行き方も変なテンポの小細工はなく、ヴィヴィッドなSchönbergのアレンジを十分に堪能させてくれます。この曲に対するサイモンの意欲的なアプローチを感じさせる良い演奏だと思います。
カップリングはこれ又サイモンらしい珍曲、L.Berioがピアノ伴奏をオーケストラ用に編曲したBrahmsのクラリネット・ソナタ1番。うーん、ロジェストヴェンスキー盤、ヤルヴィ盤に勝るとも劣らない凝りようですね。尚、ジャケットはシーレのDie Vier Bäume (1917)。
INT960.917

91.4 Hans Rosbaud-Studio, Baden-Baden 12:21/8:15/9:34/8:39
これはギーレンらしく凄く引き締まった演奏(と言ってもオーケストラの響きは重厚ですが)。Brahmsの演奏に不可欠とも思えるフレーズのちょっとした「ため」みたいなものが削ぎ落とされ、純粋にオーケストラの響きとして表現されています。ドライな演奏であればツェンダーの演奏がその最右翼ですが、ギーレンの場合、ドライと言うのではなく、確かに即物的な曲の捉え方ではあるもののある種の熱気を持った表現的傾向を持っていて重い切れ味と重厚な響きは独特です。第1楽章は速めのテンポで、特にそうした傾向が顕著。終楽章もインテンポの充実した演奏で、現代の何でも良く聞こえる(少なくとも録音上では分析的に聞こえる)響きではなく、オーケストレーションのマッスとしての響きがSchönberg自身が思い描いていた響きに近いのかな、と思います。
ここではギーレンについていくオーケストラの馬力も凄いですね。カラフルな色彩感を感じさせる音ではないのですが、芯のある強靱な響きで、特に地をはうような低弦が前に押し出す圧力となって迫力があります。
恐らく全体の曲の雰囲気は、このギーレンの演奏が初演のクレンペラーの演奏に最も近いのではないでしょうか。勿論オーケストラのバランスはかなり違っていて響きはより重厚で現代的ではありますが、表現主義的な響きと即物的なフレージングは、現代のある程度距離をおいて純粋に音楽的に演奏されたものとは違って、戦後も暫く残っていた体感的な現代音楽の演奏スタイルを感じさせるように思われます。
カップリングはお馴染みのWebern編によるBachの「6声のリチェルカーレ」とSchönbergによるJ.Straussの「皇帝円舞曲」室内楽版という新ウィーン楽派からみの正統的曲目。
RIS 110108

91.10 Conservatoire Royal de Musique, Liége 15:08/8:58/10:44/9:19
全体に遅めのテンポをとっていますが、間延びした感じではなく、音の作りは端正で美しく落ち着いたイメージ。ためのきいた独特のBrahms的イディオムもくどくならず上品にまとめられていて、楽譜を丁寧に音化していく極めてノーブルな演奏だと思います。楽器の音も落ち着いた淡い色合いで美しく、2楽章での連綿と繋がる木管と弦のやり取りや3楽章前半の弦は音響的には拡大されているもののBrahms的です。また、全体にあまりコントラストを強調しない流麗な演奏で、SchönbergよりもBrahmsの味わいを全面に出した演奏といえるかも知れません。特徴はやや薄いかも知れませんが、伸びやかな歌い口とオーケストラバランスでSchönbergの派手なオーケストレーションを上手く流れの中に取り込んでいて聴いていて安心感があります。(でも、決して特徴のない平板な演奏ではなくて、結構迫力もあります。)
オーケストラは、音色といいアンサンブルといい非常に優秀。響きは結構厚めですが重くはありません。この辺はオーケストラの特質でしょうか。
私はこの指揮者とオーケストラの組合せで同じRicercarレーベルから出ているSchubert交響曲第10番しか聴いたことがありませんのでどういう演奏をする人か分かりかねるのですが、少なくともこの演奏からはきめ細やかな端正な音楽を作る指揮者のように感じます。Brahmsの2番あたりが似合うような感じですね。
カップリングはハンガリー舞曲からBrahms自編の1,3,10番。Schönbergの編曲物に走らないであくまでBrahmsにこだわったところが何かこの人らしい気がします。
ADW 7303

93.9.6L Antwerp, de Singel 12:17/7:44/9:19/8:30
オーケストラはJeune Philharmonie = Jonge Filharmonie = Young Philharmonicで無理して訳せば青年オーケストラでしょうか。89年にR.Zollmanによって設立されたベルギーの団体でツェンダー盤でのユンゲ・ドイチュpo.のような若い演奏者を集めた団体のようです。指揮のヒルシュは1956年生まれのドイツの指揮者。ライナーによるとフランクフルト時代のギーレンのアシスタントとして勉強したとあります。
ヒルシュの指揮は要所のアクセントをしっかり付けた非常に歯切れの良い若々しい演奏で、テンポも心地よいスピード感があります。総じて厚めの鳴らし方ですが楽器は開放的に鳴ります。音の分離を精密に聴かせるというタイプではなく曲全体を大きく見据えて躍動感を表に出したなかなか意欲的な演奏だと思います。モノトーン的な締まった筋肉質のギーレン盤と比べればオーケストラの響きは格段に明るく、金管の映えた演奏は原色の色合い(丁度ジャケットの絵のような)を感じさせます。
終楽章はライヴ特有の気合いの入った快速テンポで、録音の完成度と言う点ではバランス的にも精度的にも若干荒い印象ですが、それよりこの手の若いオーケストラに特徴的な妙な癖のないストレートな音と勢いが新鮮です。決して一般的な演奏ではありませんが一回性の記録としてでも楽しく聴けました。
なお、演奏後に拍手も収録されており、実際の演奏は表示のタイミングよりやや短い(8:10位)。
カップリングはチャールダーシュとの関連でJanacekのラシュ舞曲集とJ.Straussのポルカ「ハンガリー万歳」op.332という舞曲系の組合せ。
452 050-2

95.3-4 Konzerthaus, Vienna 12:08/8:06/10:57/9:03
ドホナーニの演奏としては2種目にあたるもの。クリーヴランドo.との演奏は元々音盤化される予定ではなかった筈ですから、本人の気分としては初めての録音と言っても良いでしょう。正規録音だからということでもないでしょうが、クリーヴランドo.との幾分平板な演奏とは見違えるくらい意欲的で、曲全体の構成感とコンセプトの違いがはっきりわかります。第1楽章はクレンペラー盤とほとんど同じタイミング、小気味よいテンポでメリハリの利いた厚みのある演奏。第2楽章もえてして間延びしたような印象の薄い演奏になりがちなところを速めのテンポで通す。一転、第3楽章は十全にこのオーケストラを鳴らすことを主眼にしたような演奏で、Brahms的な粘る哀愁を表現するためのVPO.の語彙をすべて使い表現したかのよう。
終楽章のテンポは基本的には速めですが、ジプシー的な中間部、エンディング前のカデンツァ風部分との対比は見事です。これは単にテンポだけの問題ではなく、演奏方法のコンセプトがしっかりしているためでリズミックな部分とメロディアスな部分が違和感なく流れに乗っています。
ドホナーニの指揮はそれ程特徴的ではないのですが、とにかくVPO.をここまでドライヴした手腕は素晴らしいと思います。何かやる気のあるVPO.を久しぶりに聴いたという印象です。
収録されているのはBeethovenの弦楽四重奏曲第11番ヘ短調op.95「セリオーソ」のMahler編曲版、結構ハードな内容です。
09026 6865

95.3 Jones Hall, Houston 14:54/7:56/11:35/9:02
機能的ですっきりとしたオーケストラの響きはBrahms的というよりSchönbergのオーケストレーションの華やかさをより感じさせるもの。複雑なオーケストレーションは録音が良いこともあって分離も良く切れがありますが、響きは無機的ではなくかなりのアゴーギクがあります。特に3楽章はかなり粘った遅いテンポで十分に歌わせた演奏と言って良いでしょう。終楽章も大きく揺れるようなテンポの収縮があり、やりすぎぎりぎりの濃厚な表情付けですが、それでも決して古くさいスタイルではありません。エッシェンバッハの指揮というのはそれ程聴いて来なかったのですが、昔のMozartでのピアノの印象が残っているせいかこれほど濃厚な味付けは少し意外な気がします。どこかでエッシェンバッハは指揮者になりたくてピアニストになったと言うような話を目にした覚えがありますが本来こうした演奏がこの人の方向だったんでしょうか。やりたいことをしっかりやっているという意味で非常に特徴的で面白い演奏です。
カップリングはSchönbergのオーケストレーションによるBachの3曲、前奏曲とフーガ「聖アン」BWV.552、コラール「装いせよ、わが魂よ」BWV654、コラール「来たれ、創り主、聖霊なる神よ」BWV.631。
8.770032

96.2 Concert Hall, Sydney Opera House, Sydney 14:35/8:17/9:30/9:23
E.デ・ワールトのシドニーso.との演奏は、オーケストラに不安がありましたが、技術的にも何の問題もなく素晴らしい響きで楽しませてくれます。そして、昔から録音がかなりあるにもかかわらずあまりにも話題に上らないデ・ワールトがバランスのとれたコントロールで立派な出来。この人のPhilips録音以降のものは総じて響きをコントロールして、オーケストラを気持ちよく鳴らしているように思います。オランダRpo.とのWagnerやMahler、ミネソタso.との録音などは、良いものが少なくありません。
1楽章から3楽章まではゆったりしたテンポで、しなやかな作り。終楽章は少し速めのテンポ。どこといって作為的なところはなく自然な音楽。派手ではないですけれどどの音もしっかり聞こえるバランスです。オーケストラも鳴りが良くしっかりとコントロールされているという印象。Brahms的な旋律もどちらかというとあっさりとしていて殊更強調することはなく、それより重層的な響き、音の広がりを大事にしているような演奏です。コーダへの入りやテンポも理想的だと思います。こうした中庸に聞こえる演奏は面白味がないと感じられがちですが、ここでのデ・ワールトは小細工なしにオーソドックスな解釈できちんとオーケストラをドライヴしていて、非常に安定感、安心感があります。整ったフォルムの素晴らしい演奏だと思います。
このCDはメインであるこの曲の前にBachの編曲ものが3曲収められています。曲はエッシェンバッハ盤と全く同じで、コラール「来たれ、創り主、聖霊なる神よ」BWV.631、コラール「装いせよ、わが魂よ」BWV654、前奏曲とフーガ「聖アン」BWV.552。すべてSchönberg編。
ALT-006-7

97.6.23L NHK Hall, Tokyo 14:10/8:01/11:49/10:58(但し終楽章はかなり長い拍手を含めたタイミングで、実質は9:24位)
私はこの指揮者の演奏をこの盤で初めて聴きました。NHKso.の演奏は今までもいくらかは耳にしていると思いますが、私にとってLP,CDを買ったのは初めてだろうと思います。
この2CDには他にDebussyの「牧神」と「海」、R.Straussの「死と変容」、Mozartの「ドン・ジョヴァンニ」序曲が収められていて、そのそれぞれが出来不出来ということよりこの若い指揮者の今現在の似合い不似合いとでも言った方が良い居心地と曲へののめり込み方の深さを感じさせてくれます。
2曲のDebussyは今や指揮者の独自性を目に見える(と言うか耳に聞こえる)形で正統に表現するのはなかなか難しいことではないでしょうか。メルクルは雰囲気的なDebussyというよりかなり明確な意志を持って響きと構成を作っていく指揮者であるように感じます。硬質な輪郭、意識的な歌い廻しと激しい起伏の対照はこの人の特徴的な点だろうと思います。
しかし難点を言えば、盛り上げるところは迫力がありますが(「死と変容」のエンディングも同様)、聞き手には少しばかり恣意的に聞こえないでしょうか(実際演奏会場で聴けば圧倒される響きでしょうが)。
「死と変容」はDebussyと同様のオーケストラバランスと響きのコントラストを考えた独自のコンセプトを持った演奏だと思いますが、どうもオーケストラのドライブに今一しっくりこない点があるように思えます。やりたいことはわかるのですがオーケストラが音では反応しているものの要所をつかまえきれずに明確なフォルムを形作るところまでいっていないような気がします。部分では色々面白くはあるのですが、全体に指揮者の意図が逆に音楽をとりとめのない方向へ導いてしまったかのようです。R.Straussののような常に重層的に響くオーケストレーションと楽想の流れに対してこうした明確な響きと鳴りの良さを武器に演奏するのはある程度の経験がないとなかなか容易ではないような気がします。客演でのハンデは勿論あるとは思いますが。
さて余談が多かったのですが、本題のピアノ四重奏曲です。結論を先に言いますとライヴらしく気合いの入った演奏でなかなか面白く聴けました。切れ味の良いリズムとかなり思い入れの強い歌のコントラスト、大きいダイナミクス、自在なテンポ設定、実にメリハリの利いた演奏です。この人のこの曲に対するコンセプトというのは割に分かりやすいと思います。曲想の変化する部分での演奏の仕方、振り分けが非常に明快です。これは事前の構造的な設計をしっかりやって、そこから曲を組み立てていくといった感じです。
特にテンポ設定は面白い。切れのあるテンポなのですが、とにかく楽想毎に設定されたテンポがめまぐるしく変化します。第3楽章は全体にゆっくりしたテンポですが、マーチ風の中間部はかなり唐突にテンポが上がり強調されます。これは自然な流れからというのではなく極めて意識的に対照効果を狙ったものでしょう。終楽章も元来気分の変化が激しい音楽ですが、ここでもテンポのコントラストが大きい。びっくりしたのは終盤カデンツァ風ソロの直前、大きい下降音階の部分でここだけ異様に遅いテンポをとっています。これほど見得を切ったようなテンポの変化は他の演奏ではなかったような気がします。すごく大胆ですね。
全体にBrahms的な味わいやオーケストラの色彩感などいくつかの点で最上ではないにしろ、とにかく管弦楽として実に見事に構成された演奏と言えると思います。
3-7493-2 H1
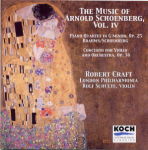
98.10 Abbey Road Studios, London 13:49/9:06/10:59/8:52
R.クラフトは60年代にこの曲を録音しているようなのでこれが2度目の録音ということになります。クラフトと言えばStravinskyの一連の録音が有名ですが、最近KochにSchönbergの作品を網羅的に録音しており、これはその中の1枚、vol.4にあたるものです。
第1楽章から第3楽章までは割とゆったりした運びで、丁寧な作りという印象が強い。特に第2楽章は、テンポよく進めていく演奏が多いのですが、クラフトは比較的遅いテンポでバランス良くオーケストラを鳴らしているので、音楽の大きな流れを感じさせます。聴いていて安心できるというか、心地よい気分にさせてくれます。
終楽章は、前3つの楽章とは少し違って若干速めのテンポをとっています。まず感じるのが、派手にはならないものの非常に良く考えられた音響バランス。そして無理のないアゴーギクと細かいテンポの揺れ。これは指揮者の周到な計算が働いているのでしょう。絶妙な抑揚が音楽全体を息づかせているように感じます。
全体にSchönbergの派手なオーケストレーションを強調することなく、細やかな気配りが行き届いた演奏といえるでしょう。音響的にも非常に良く整えられた音で、一見面白さは薄く感じますけれど、実は鳴るべきところは鳴っていて聴き応えがあります。このあたりがSchönbergのスコアの隅々まで知り尽くした人の手による老練な技でしょうか。こうした演奏は決して一朝一夕に出来るものではなく、それなりの経験の積み重ねによって初めて可能なんでしょうね。この曲のスタンダードになり得る素晴らしい演奏です。
尚、蛇足ですが、リーフレットのPO.のメンバー表に、Hugh Beanの名前が見えるのが感慨深いですね。
カップリングはSchönbergのヴァイオリン協奏曲。
CD1140

2000.4 Louis de Geer Hall, Norrköping, Sweden 13:46/7:33/10:38/8:54
BISからリリースされた盤。私は指揮者のLü Jiaという人は初めて聞きました。名前からもわかるように東洋系で、ライナーによると1990年Antonio Pedrotti Competitionに優勝して以来ヨーロッパで活躍しているそうです。演奏は非常にオーソドックス。でも型にはまった面白味のない演奏ではなく、オーケストラは良く鳴っていますし、何より演奏に張りがあります。管や打楽器が突出することなく、実にしっかりとしたバランス。面白いのは、この指揮者、結構細かく楽器のバランスをコントロールしているようで、オーソドックスながら響きは実に新鮮な響きが聞こえます。
第2楽章はかなり速めのテンポ。リズムが軽やかでサラッとした印象。3楽章以降もBrahmsの音楽ということで度々付け加えられる過度の歌い廻しなどは見られず、かといってSchönbergのオーケストレーションをやたら派手に鳴らす訳でもありません。こうした一見淡々と演奏できるというのは、現代の若い指揮者にとってこの曲が、他のSchönbergの曲と全く同じように、更にBrahmsの音楽を下敷きにしていると言うことでは尚更に古典的なアプローチで接することの結果であるんでしょうね。
この演奏で唯一特徴的なのは、終楽章コーダ部分をアッチェランドするところです。これは最後になって少し意外でした。このあたりにこの指揮者の音楽の作り方と表現の仕方の若干のギャップというか、ちょっと唐突な感じがしますが。
とにかくあまり奇を狙ったところのないしなやかな音楽の作りには感心します。それでいて陳腐な響きにならないところもこの人の力量でしょう。面白味には若干欠けるのかも知れませんけれど、非常に良い演奏だと思います。こちらの方が少しテンポ設定は速いのですが、バルトロメ/リエージュpo.に見られる端正な響きの肌触りに似た感じを受けました。
最後にこの最新録音、流石にBIS、音が良い。ノールショッピングso.もこれほど上手いオーケストラだったのかと再認識しました。録音の上手さもありましょうが、しっとりとした美しい音で技術的にも申し分ありません。
カップリングの方はすごく凝っていてBrahmsの「4つの厳粛な歌」とコラール・プレリュードop.122から2曲、いずれも名指揮者E.ラインスドルフがオーケストラ用に編曲したもの。(ラインスドルフってこんなこともやっていたんですね。初めて知りました。)このうち前者では Olle Persson というスウェーデンの若手バリトンが歌っていますが、伸びやかな明るい声質で素晴らしい歌を聴かせてくれます。
469 409-2
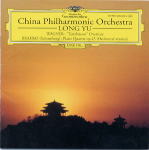
2000.11 中国、北京、保利劇院 15:20/8:16/11:40/9:46
中国国内でのリリースで、何とDG盤です。ツェンダー盤は元々DGからリリースされたものですから(CDはDGから出ていない)2種目となるんでしょうか。指揮は余隆(Long Yu)、オーケストラは中國愛樂樂團(China Philharmonic Orchestra)となっています。
指揮者の余隆は1964年生まれ、上海音楽学院、ベルリン芸術大学に学び、現在は海外のオーケストラも指揮しているようです。中国フィルハーモニック・オーケストラは2000年に設立されたという非常に新しい団体ですが、団員120名を擁する大規模なオーケストラです。
新しい録音ですので、録音はそこそこ良いのですが、全体に少しぼってりとした印象があります。若干マイクがオフ気味で、編成が大きい割りに歯切れの良い演奏ではないので余計そういう印象となるのでしょうか。音符をきちんと再現しているにもかかわらず、Brahmsがこの曲に込めた暗い情熱とか、ひょっとしたら晩年のSchonbergが編曲という形で重ねたであろう遠い情熱がほとんど伝わってきません。偏見を持っているつもりはないのですが、これはオーケストラの機能性の限界なのか、指揮者の技量と資質によるものなのかはわかりません。何かもどかしさを感じさせる演奏なのです(ティルソン=トーマスの演奏を聞いた後だったので特に・・・)。
因みに、Johannes Brahmsは「約翰内斯・勃拉姆斯」、Arnold Schonbergは「阿諾爾徳・勛伯格」、そして曲名は「G小調鋼琴四重奏 作品25號」と書くそうです。カップリングのWagner「タンホイザー」序曲は「理査徳・瓦格納」作曲「唐豪瑟」序曲。
また、シェーンベルク・アーカイヴのディスコグラフィによると上記以外にCD化されていないアナログ期の録音が3種あるようです。
R.クラフト/CSO.(66?)(CBS)・・・この曲の初めてのレコーディング
G.シフラ jr./ブダペストso.(Pathé)
G.ロジェストヴェンスキー/ストックホルムpo.(79.2.9)(Melodiya)・・・ロジェストヴェンスキーの1度目の録音。